|
|
|
�������̗�
���҂͈�ɐ��A��Ɏp�A���܂��ɐ��悯��Ⴀ�p��������������B
���[�f�B���O�͂��̘_�@����ԑf�p�ɔ������鉉���\���ł͂Ȃ����Ǝ��͍l���Ă���B
�Ƃ����킯�Łu�f�p�ȉ����v�Ȃ̂��B
���������ꂪ���͋ȎҁB
�o��l���Ƃ����u�{�J�V�v�����炸���Z�Ҏ��g���ϋq�̑O�ɘI�悳���̂�����B
���Ⴀ�A�������̂��̂��o���Ηǂ����ƌ����Ƃ���̓A�E�g�B
���l�̎����犴����ɒN����X�t�����������ȂȂ��B
�ŋ��̉��Z�ł��������̂��̂��o���̂������Ɗ��Ⴂ���Ă�̂��������B
�\���Ȃ�Ă���Ȏ��Ȗ����I�ȊÂ�����Ȃ�����B
�������u�����v�ɂ���A�܂莩����鑶�݁B
���́q���݂���́r�A���肫����̌��t�Ō����q���݊��r�A������̌����u�ԁv�A
����邽�߂ɂ͐��U�C�ƂȂ̂��B
�o�D�͎�����g�����X�i������j���āu�����Ȑg�́v�A�܂�[����Ԃ̃��f�B�A�i�}��j�ɂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�܁A�C�^�R�ł��ˁB
���ҁi�����ҁj�̑㗝������̂�����B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�o�D�̑��݊��Ƃ́H
�o�D�≉�Z�҂́q���݊��r��N�ł��������A�܂�œV����~���Ă������́i�V���̂��́j�ɂ��Ă��܂��B�������A����
���Z�p�̖��Ƃ��ĉ����l�ފw�̎��_����ڍׂɕ��͂����̂��o���o�́w�o�D�̉�U�w�x�B����X�^�j�X���t
�X�L�[�̐g�̍s���̕��́A�O���g�t�X�L�A�o���o�Ƒ������Ō��ѕt���Ă���B
�������Z�s�ׂ̌|�p�ʂł̒T����30�N�ȏ㑱���Ă������Ƃ̒��S�ɂ���̂����Z�҂́q���݊��r�l������@
�I�ɋ�̉����邱�ƁB�o���o���Q�Ƃ������{�̓`�����Z���q���g��F���g���[�j���O��҂ݏo�����B�o���o��m
��̂�15�N�O�A����X�^�j�X���t�X�L�[�͍ŋߐ��E�ŔF������O�シ�邪�����ۑ肾�B
���݂ɖ��҂́q���݊��r�̂��Ƃ𐢈���́u�ԁv�Ƃ������t�ŕ\�����B���̑��Ƙ_���́u������ƃA���g�[�v�A�S��
�����ɐ�����Ɋւ��Đ������ӋC�Ȃ��Ƃ����������S�������͖ʔ������Ă��ꂽ�B���ӋC�������蔽���ГI��
�ԓx�ɗ���������̍L���搶�������B���́u�ԁv���u�G�l���M�[�v����T�������B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
���N�̓e���E�A�[�c�E�t�@�N�g���[�i��ɂ��鉉���c�́j��n������30�N�A
�u�W���������z���A�����z���v���������O��
�R����J����A�����Ē����x�~��������
20��̎�҂������S�Ŏn�߂������A
��O�̊ϋq���u�����i��ꁁ�V���A��G���^�[�e�C�����g�E������j
�����Ă܂���܂����B
���ꂩ��͑��N���W�c���߂����A
�I���W�i���n��㉉�A
���E�̌���Y�ȏ㉉�A
���[�N�V���b�v�x�[�X�̏W�c�n��
�ȂǍ��܂œ��l�ς�炸�̊������s���Ă��������Ǝv���܂��B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�u�����n�悩�琶�܂ꂽ�����V�v
�ŏI���A�V�A�^�[�J���t�@�����X�iITI���{�Z���^�[�{���ۉ����]�_�Ƌ�����{�Z���^�[�A�g���j�I����A���
�O�ŋL�O�B�e�B�X�[�_�����痈���̃A������A�t�B���s�����痈���̍�ƃ��f�B����ƃV���A��i�㉉�`�[���i�V
���C�P�C�^�A�ɓ��O�q�A�u������j�A���̓��i�̉��o�ɓ��傳��A���R�Ђ�݂���A�i��̎����p�コ��A��
�ۉ����]�_�Ƌ����̐V���L����A�C�s�̎Ⴋ��]��萒q�q����A�ʖ�̎O�ւ���Ԃ���A�V���A��i�|
��̉L�ˑ�����A�����|�p���ꕛ�ْ������G����炱��܂��ő��ɏW�܂�Ȃ����ȖʁX�A�����낢�B�C�O��
��̃Q�X�g�͓��{�̉����E��S���d�v�Ȑl�X�Ƃ���5���Ԃ̔M���C�x���g���Ƃ��ɂ����B

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�X�[�_�����痈�����ꂽ�A���E�}�t�f�B�E�k�[�����i���o�ƁA���l�X�R��g/���a�|�p�Ɓj���͂�ŁB���̓��A�A����
��̃��[�N�V���b�v��10������15���܂ŁA���N�`���[��16������18���܂œ����|�p����M�������[�Q�ōÂ��ꂽ�B
���[�N�V���b�v���l���W�܂�A�C�x���g�ӔC�҂Ƃ��Ă͋����Ȃł��낷�B������w�ŃA�i�E���X�����ۂɁu�����n��
�����v�A�u�t�H�[�����V�A�^�[�v�Ƃ������ƂɊS�������ĎQ�����Ă��ꂽ�l�X�����ĉ����̊O�ɍL���������Ƃɒ�
�ځB���N�`���[�ɂ�ITI��̉i�䂳��i���v���c�@�l�������╶�����c�������j�AITI���ƈψ����̍�������
�i�����|�p����A���ْ��j�����ȁAITI�]�c�����ǒ��A����̋g�₳����o�ȁB�Q���҂��f���炵���ʁX���W
�܂����̂��B

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�����n�悩�琶�܂ꂽ���� �V���[�Y7
���[�f�B���O�����N�`���[
�u�����Ɛ��E�\���{�Ɛ��E�̏o����߂����āv
2015�N12��16��(��)�`20��(��)
�����|�p����A�g���G�E�G�X�g�i�ꕔ�ʉ��j
���������v���f���[�X�A��N�ȏ�̏������₵�Ă悤�₭�H�蒅�����N�Ɉ�x�̔N�����A�����̓��u��
���n�悩�琶�܂ꂽ�����V���[�Y�V�v���悢�捡���A��������B�����̊Ԃ͒����Ȃ��A�Ǝv�������Ă��܂��Ƃ���
�Ƃ����ԁA�܂�Ől�̈ꐶ�B
����̗�����w�ňقȂ�̈�A�����̊O�ɂ��ĉ��������Ă���l�X�̘b���Ȃ���A�u���������v�Ƃ͉���
��v�Ƃ����֊s���������������茩���Ă������������Ă���B���Ԃ�����A���̊��Ō��킳�ꂽ�M�d�ȑΘb
�i�g�[�N�A���N�`���[�A�V���|�W�E���A���E���h�e�[�u�������Ȃ�̕��ʂŎ��{�A��������H����Șb���C�O�Q
�X�g�����čs���Ă����j�ƂƂ��ɂ܂Ƃ߂Ă݂����B
�z�[���y�[�W��http://iti-japan.or.jp/conflict/
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
���{���o�ҋ���E���ۉ����𗬁u�f���}�[�N���W�v�ŏI���̃��N�`���[�ƃV���|�W�E���ɑ����^�B�u�����ƃ|
�X�g�h���}�v�A�u���㉉���̉ۑ�A����K���v���e�[�}�B
���Ƃ���l�X�̐����͐����Ɛ藣�����ƂȂo���Ȃ��B�����͐l�X�̐�����ʂ��Đl�Ԃ̂���l��p�̐^
����Nj�������́A�Ƃ���Ȃ牉�����邢�͌|�p�Ɛ����͕s���̂��̂Ǝŋ����n�߂����납�炸�������ƍl��
�Ă������A�c�O�Ȃ��玄���w������i������͑S�����̌�́u�V���P����v�Ƃ��ɑ�����炵���B�����̓V���P��
��ɂȂ˂�����Ƃ�������ɔ������Ă��������Ȃ菭���h��70�N��㔼�`80�N���20��ȁu����v�j����
�ӂ���w�Z�ŗF�l�Ɛ����̘b������̂̓^�u�[�A�Ƃ������_�T���A�ꂪ�V���P��Ƃ����������o���オ��A�ȗ�
���\�N���ꂾ��������A��҂��ϋq�Ώۂɂ��鏬���������ȕ����B�ނ��A��������Ă���l�Ԃ͒N������
�̒��ς������Ǝv���Ă���B���Ȃ��Ƃ��u�����Ȃ���Ă�������́H�v�ƌ����Ă��܂��Љ�A���𒆐S�ɓ�����
��ł͂Ȃ��A�����Ɛl�ɂ͑�ɂ�����̂���ł���݂����ȁA�����������̒��ɕς���ė~�����Ƃ����v���ł��
�Ă���Ǝv���B���ꂪ�����ƂȂ���Ȃ��̂͗l�X�Ȏ�����邪�A�悤�₭���̖ڂɌ����Ȃ��u����K���v����
�蕥������̂�3.11�ȍ~�ł͂Ȃ����B����͎��̎v�����{�I�����́u����K���v���ł����B
�����̂���l�A�����P����A�}�X����̂��b���Ă��āA��������A�ږ���肪�l��i���ʁA�r���j��
��Ƃ��ĎЉ���Ă���n�Ō|�p�𐭎�����藣���čl���邱�Ǝ��̂��u���Ԕ��v�Ɗ������B����͍��ې���
�̘_���ŐU��ꋓ��̉ʂĂɓ���ɔ��e��U��܂���Ă��܂������n�ł������ł���B�B�B

���V�h�ł̑ł��グ
���L��28���̃��[�f�B���O�w�}�j�t�F�X�g2083�x�i��F�N���X�e�B�A���E�����P�A���o�F����Y�A�o���F��}�m�����j��
���z�������c���Ă����܂��B
�ƂĂ��h���I�ȍ�i�Q�ł����B
11��27���L
�i�ς�O�j�����̃��[�f�B���O�́w�}�j�t�F�X�g2083�x�i�N���X�e�B�A���E�����P��j�A�m���E�F�[��77�l�E�Q�̘A���e
�����N�������ň��̃m���E�F�[�ƍߋL�^��������L���X�g��������`�҃u���C�r�N�̏����L�����h�L�������g�e
�L�X�g�����ɍ��ꂽ��l�ŋ��A�Ƃ��������m�v���C�̂悤�ł��B�����Ƃ��Ă͈��p�\���^�̃C�F���l�N�n�ł��傤
���B19���A�|�\�ԓ`�ɁA500�~�Ƃ����j�i�����I�₢���킹090�|6510�|5549�i�S���F���X�j��Ƃ̃����P����
��1973�N���܂�A�ŋ߂̓o���G��I�y���E�C���X�^���[�V�������肪���A�[�g�̋��E������s�������Ă��銈��
�����Ă���Ƃ��B�f���}�[�N�Ƃ��������������X���͐��E�e����30��`40��O���̉�������̋��ʓy�U�̏��
����Ƃ����̂�90�N��ȍ~�������瓌���̉��������n�Ō��ĉ��A�ŋ߂̓A�t���J�⒆�����t�H���[���Ă��邨
����̌����B1960�N����̉������O���g�t�X�L�[�ȍ~�̔��������S��`�j�ς̏�ɗ����������̉�����A
1990�N��̃~�����[�ȍ~�̕����ƃt���}���i�x���M�[�E�I�����_�ꌗ�j���甭�����h�C�c�ɔg�y�����|�X�g�h���}��
���n�̗��ꂪ����������1970�N�ȍ~�ɐ��܂ꂽ���E�̉����l�ɋ��L���ꂽ�����ߑ�j�ρ`�ߑ㌀�̐�ɂ�
�鉉���Ƃ������ʊ�Ղ̏�ɂ��鉉���A�Ƃ����������Ǝv���܂��i�ނ́w�m�[�}�����C�t�x�Ƃ�����i�����Ă̈��
�ł����j�B
(�ς���)����̓m���E�F�[�̔���������`�i�ɉE�j�̘A���e�����X�g�A�u���C�r�N���c����1500�y�[�W�ɓn�镶��
�Ɣނɋߐڂ��Ȃ���n�삳�ꂽ�w�}�j�t�F�X�g2083�x�̃��[�f�B���O���ς��B�C�X����������̈ږ��𑽂������郈
�[���b�p�B�o�������猩���ꍇ�A���\�N��ɂ̓C�X�����n�̕��������h�ɂȂ�\�������蓾��B���̎��A��
��i�����j�����[���b�p���ŋN���邱�Ƃ����蓾��i�ƃu���C�r�N�͊�@�����o�����j�B���̍�i�ł�'�ށi�u���C�r
�N�j'�̌��t�����/�����鎄�͉��҂��A����艻����Ă���B�����ɓ��{�l���҂����̖₢�̑O�ɗ�������Ă�
�܂��B�ʏ�̎ŋ��ł͐��݉����ĕs��ɕt����鍪�{�I�Ȗ₢��������艻�����\���������Ă���B��������
�Ď��������ގ������̌����]���A�ǂ��l�߂�ꂽ�ɂ���A�܂�\���Ƃ��Ă͂��ł������҂ɂ�
�肤��̂ł���B�̂��̂��ƈ��S���ɗ��܂邱�Ƃ͏o���Ȃ���������Ȃ��B�e�����X�g�ɂȂ邩������Ȃ��̂��B�u��
�͎��ł͂Ȃ��v�Ƃ����ۏ͂ǂ��ɂ���̂��H�����Ƃ͖��W�ȏo�����A����������Ȃ��B���̂悤�Ȗ₢��
������艻��������i�ł������ƌ�����B���X�A�����ƌ|�p��ʌɕ���������ǂ��炩�̗D�ʐ������������
�ł��Ȃ��B�o���͕s���Ȃ̂��B���ɕ����n��╴���̌��ʂ���Ƃ��ĉ����Ă��郈�[���b�p�ł͐�����
�|�p�ْ̋��W���ɂ��Č|�p�s�ׂ��l����̂͌������ꂵ�Ă���B��������A�|�p����Ƃ����̂����S��
�Ɏ����̐g��u���A�u������̂ł͂Ȃ����Ƃ����m�ɂȂ�B�ɂ߂Ďh���I�ȍ�i�ł������B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�����䌒���ʂ�̉�ɏo�ȁB
�I�ɚ����z�[���E���r�[�Ł����䌒���ʂ�̉�A���̌�A���䂳��Ȃǂł悭���p����Ă�
�����ؗ����X�u�����I�v�Ɉړ����āu���䌒����ƌ�炤��v���Â���A100�����鉉���W�҂��W�������B
���䌒����Ƃ̏��߂Ă̏o���30�N�ȏ�O�̑���c��w6���قT�K�A�g���G�ɑk��B�����͓����A��������
�������_�ő��䂳��͑��吶�Ō������ꂽ���c�i�u�����W�c�A�W�A����v�j�̕���ɑ����^��S�������]��
�����Ă����������i1984�N�̑��䌒����̌��]�ˁ@http://forest5.ojaru.jp/page020.html�j�B
���䂳���1982�N���璩���W���[�i����T�������Ɍ��]���������悤�ɂȂ����Ƃ̂��Ƃ����猀�]�ƂƂ���
�̃L�����A���X�^�[�g����������̍��ɏo���킵���Ƃ������Ƃ��낤���B���̌�A�悭����������ꂽ�肵�����A��
���������߁i���{�́j�����̏ꂩ�������ĊC�O�ȂǂŊ������鎞���ɂ͉����r�₦���B�悤�₭�ŋ߁A����
�����ŏo��ꏏ�Ɏ������킷�@����o�Ă������B�B
�ǂ������ڂ��C�̂��������䂳��炵���A���̓��̉�͘a�₩�ȃ��[�h�Ɉ��A���̂������v���Ԃ�ɉ�ʁX
�Ǝv���o�b�ɋ������肵���B���䂳��Əo���킵������6����5�K�A�g���G�͌����̂S�K����ɑ傫�Ȗؑ�������
�����A���̒��ɎO�̃A�g���G�������āA���ꂼ��̃A�g���G�Ō������ł��Ƃ��o�����B���X�́u���R����v��
�g���Ă�����Ԃ����A���U��A�����̉����l���ʉ߂����ꏊ�ŁA����ł́u�����v�A�u�ؗ�v�ƕ������̃��b
�J�ł��������B
6���قT�K�A�g���G�́u���R����v���U��A�������ւ�����̌��c�Ȃǂ��g�p�A���̓��̂��ʂ��ɏo�Ȃ��ꂽ
�B���H�[�E���{�͂����6���قł͑��y�B�����|�p����̍����G����́u���̗V���Ёv�n���O�A���������_��
���Ă������c�i�u�R�n�����v�j�ɂ��Ď������̌��c�Ƃ́u�����W�v�Ƃ������������͒핪�A���b�p���̗�ؑ��N��
�������m�Ï�ɂ��鎞������̃��W�i�A���⌀�c�͈Ⴄ���u�����v�����ԕ��A���c�����m�̌𗬂��������肵
���i���́u�����v�̊ԕ��̓L���������{�b�N�X�̐���N�܂ő����j�B
�Q�O��̍��̎v���o���S�点�Ă��ꂽ���䂳��͍ŋ߂��Ⴂ�����ϋɓI�ɉ����A���ɂ͌��������B�ʼn����E
�S�̂̂��Ƃ�^���ɍl�����Ă����B�����삯�o���̂���K��@���ꂽ��l�����A���̎p���͏I�n�ς���Ă�
�Ȃ������̂����̓��̎Ⴂ�i�Ƃ�������������j�̉����l�̘b������m�F�o�����B���������M�ӂ����]�_�Ƃ�
���A���ɂ���̂��낤���H���Ƃ��₵���C�����ł���B
�ƂĂ��g�����ȉ�ł����B���䂳��̐l���ł��ˁB
������ł����B�ƂĂ��g�������͋C�ŁB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�����{�̈��S�ۏႪ��]�����ꂽ��
��
������`�̓y�䂪���ꂽ��
�^�}�A���@�ᔽ�̖@���𐔂̗͂ʼn����ʂ��E�E�E
�����ƕς��Ȃ��V�h�A�y�j�̒��B���s�ɗ��������̐l�X���s�������B�����Ǎ���܂ł̌i�F�ƍ��������
�i�F�͈Ⴄ�Ǝv���Ă���B�����Ⴄ�����l���Ȃ��琶���čs�������Ǝv���B
����͍���O�ňꐶ���������グ�鍂�Z�������̏��X�����b�����Ƃ��ł����B���܂ł��܂�O�ʂɏo�Ȃ�
�����V�[���Y�̏��q�w���́u�l�O�Řb���̂͋��Ȃ̂����ǁv�Ƃ����₢�|���ɂ������X�s�[�`���������B����
���������悤�ɐ����グ�悤�Ƃ����Ƃ������@���ׂ����A���i�S�w�A�Ƃ��A�����h�Ƃ�������j�̖��������
���Đ̂Ȃ���́u���{�œ|�v��40�N50�N�ς��Ȃ��V���v���q�R�[�����グ�Ă����������������菭���ɂȂ��Ă�
��̂œ������i����ȋC�����͂���܂ň�x���N���Ȃ��������j�B
11���ɖ^�Z�Ō��������B���ڂ͂܂����m�o���Ȃ��̂������߂č��Z�����̋Y�Ȃ��g���B�o�ꂷ��͍̂��Z
���A���ꂪ����B���̒n��K�ꂽ���Z���i���q�j�����͑������̒��ŏ����Ȑ푈���n�߂�B
�u�푈�͐l�̐S�̒��Ő��܂����̂ł��邩��A�l�̐S�̒��ɕ��a�̂Ƃ�ł�z���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�B���l�X
�R���͑O�����A����E���̎S�Ђ̒����琢�E�̕���l�̘A�тƓ�x�Ɛ푈���N�����Ȃ��Ƃ�����
�ӂŐ��܂ꂽITI�i���ۉ�������j�Ɏ^������20�N�ȏ�O�Ƀ����o�[�ɂȂ����B����ITI�i���{�Z���^�[�j�̊��Ƃ�
�āu�����n�悩�琶�܂ꂽ�����v�i12��16���`20���j�̏������{�`�{�`�Ɛi�߂Ă���B����܂łƕς�炸�n��
�Ȋ��������A�u�����v�̋������Ӗ����n�߂�����7�N�O�Ƃ͐����ς�����B
���N�̓V���A�̍�i��\�肵�Ă���B�t�B���s���A�i�C�W�F���A���B�����ăt�B���s�������Ƃ�����B�X�[�_������
�́u�����Ɖ����v�̃e�[�}�Ɏ��g���������Ă��錀��ƁE���o�ƁiITI�{������j���������Βk�Ȃǂ�\��
������B
�����₩�Ȃ�����邱�Ƃ������Ȃ�Ɉ������Ă��������B
�l����A�����ɖ₢�|���Ă݂�A���������_�C�A���[�O�̏ꂪ�������Ǝv���B
�l�|������G�����������A���Ȃ��Ƃ�����������ł͂Ȃ��B
�������ǂ��Ƃ��낾�Ǝv���Ă���Ă���B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �ߌ�2������X�^�[�g���w�Njx�܂��ߌ�9���܂ő������A����8��9���̔��\�߂����āu�t�N�V�}���p���X�`�i�o
�R���E�����āv�Ȏŋ������ꂽ�B�u����͍ŏ��̈���A���Ƃ͂��O�����Ŕ��W������v�Ƃ̓C�n�b�u�BWS��
�͌S�R���s�ψ��̍����I����ɘA����āw�R���A�x�ɁB�X�̍ݓ��O���A�E�N�i�`�����E�����`�����j����̓p
���X�`�i���痈���C�n�b�u�ɔM�������ƘA�т̃G�[���B��l�͈ӋC�����B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
��Ɏ��������������y���܂��Ă����C�n�b�u�Bin �S�R�ł�WS�v���[���e�[�V�����i���\�j���}�����邱�ƂɂȂ�
���B�����Ƃ͕ʂ̑�{�w��L�����v�̎ŋ��x���g���B��{���x�[�X�ɂ��邪�A�u��{�W������v���Ƃ���肽
���Ƃ����C�n�b�u�A�t�N�V�}�I���W�i���̍�i�ɂȂ肻���B���\��8��9���i���j14������B�w�R in �P�x���[�f�B���O��
���ƂƂ��ɍ��I��{���ď㉉�B���͌S�R�s���y�E�����𗬊فi�~���[�J�������Ɗفj
�ʐ^�F�S�R�̃��[�N�V���b�v�̗l�q

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�������ł̃��[�N�V���b�v������̃C�n�b�u��FB����]�ځ�
�������� �C�n�b�u�E�U�n�_�@
2015�N8��6���@����E���ōL���Ɍ��������Ƃ��ꂽ����
�����ɂāA���ː��ƒn�k�Ƃ��炵�������W�c��
���͍����A���˔\�R�ꎖ�̌�̕����ɂ��Ċw�т܂����B�����Ő�����Ƃ������ƁA�������ː��ɂ��炳����
�������Ƃ������Ӗ�����̂��A���߂Ēm��܂����B����͐G��邱�Ƃ��ł��Ȃ��A�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��G�ƑΛ�
����Ƃ������ƁB�����Ȑ��ʌv���g�т��A���ː��ʂ��v�����Ȃ���ʂ肩��ʂ�ցA�n�悩��n��ւƈړ������
�������ƁB�ǂ̐������ނׂ����A�ǂ̐H�ו������ɂ���ׂ�������ɔc�����A�����ʂ����Ȃ�������I�ԂƂ�
�����ƁB�v���g�j�E�����ǂ����������̂ʼn��N�l�̂Ɏc�邩��m��A�܂�������5���Ԃɗ��т���ː��ʂ��A����
�n��Ől��1�N�Ԃɗ��т镽�ϓI�ȕ��ː��ʂɑ������邱�Ƃ�m��܂����B�����̐l���ڍׂ�m��Ȃ����̋ꂵ
�݂͑ς��������A���˔\�̊댯�ɒ��ʂ�������Ƃ������Ƃ́A�قȂ�`�̐�̂ł��B����͒n��ƒn���A����
�ォ����J�Ɏ���܂ŁA�����̋��X�ɂ���Ԑ�̂ł��B
�����A�������p���X�`�i�l�ƕ����̐l�тƂ́A������ꂽ�Ж�̋K�́A�����邱�Ƃւ̈��A�����ĉ���̂��߂�
�����Ƃ����_�ŁA�݂��Ɏ��Ă��܂��B�ނ���������Ɠ��l�ɁA�����̂��߁A�܂���̂������N�����ڂɌ����Ȃ�
�댯���玩���������邽�߂ɁA�����Ă��܂��B���������̒��Ɏc�邽�߁A�q�ǂ��������a�C�ɂȂ�Ȃ����߂�
�����Ă��܂��B�`���ނ͈قȂ��Ă������댯������A�ꏊ������Ă����|�͓����B���̒n����ɂ͑����̋ꂵ
�݂����݂��܂��B�Ôg�������炵�������̔ߌ��ƁA���˔\�R��̉e���́A�����N���ɂ킽���đ������̂ł��B��
������Ăӂ邳�Ƃ��̂Ă邱�ƂȂ��A���������̓y�n�Ɏc�葱���镟���̏Z���̕��X�́A���h�Ə^�ɒl����
���B
�����A������9�K�ɂ���Ƃ��ɁA�����̉��ɂ���n�ʂ��h���Ƃ������o�������Ȃ���̂���m��܂����B����
�S�ꋰ�|���o���܂������A�n�k�̗h��͓���̈ꕔ�������ŁA�݂�ȏ��āu���v�A�����ł͂ӂ��̂��Ɓv��
�����܂����B����܂őS���m��Ȃ����������̓�v�f�A���ː��ƒn�k���o����������҂��Ă���3�ڂ̐V�̌�
�́A�V�����O���[�v�Ƃ̏o��ł����B�Ԃ�����̎Ⴂ�Q���҂����̓G�l���M�[�Ɗ��C�ɖ������ӂ�A���[�N�V
���b�v�̐����Ԓ��A���͔ނ�ƈꏏ�ɂ��邱�Ƃň��炬�Ɗ�т������܂����B
���[�N�͂��܂��܂Ȗ�������o�����ł����ς��ŁA�Q���҂݂̂Ȃ���̂��炵���p�A�l������낱��Ŏ�
��A������댯��Y��悤�Ƃ��邻�̎p��O�ɁA���̔߂��݂͈ꎞ��~���܂����B
�F�l�̍������Ί�ʼnw�Ō}���Ă��ꂽ�Ƃ����A���͔߂��݂�Y��܂����B�����A�e���Ȃ�݂Ȃ���A���ꂪ��
���Ȃ̂ł��BI.Z�@
�i�|��F�n�Ӑ^���j
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
���ɍ��ۉ����𗬃Z�~�i�[���̃p���X�`�i���W�A�����ł̃��[�N�V���b�v�������}�����B�Ⴂ�Q���҂�����
�Ȃ������A�x�e�����̉��o�ƁA�o�D�������Q�����A�܂��o���G�e�B�ɕx�o���̎Q���҂̈ӎ��̍����A�ӗ~��
�����̓G�N�T�T�C�Y�̓r���ł����X�Ɏ��₪��яo���A�u�t�Ƃ̊����ȉ������J��Ԃ��ꂽ���Ƃł��̉Ă̏�
���𐁂�����M�ʂ̍����A�S�̍��������Ɉ�ۂɎc����̂ƂȂ����B�p���X�`�i�E�A���u���ɂ͂����̏�
�M�̉��x�������グ�閣�͂Ɠ䂪����ł���悤���B�C�n�b�u����o���ꂽ�G�N�T�T�C�Y�ɉ�����Q���҂̂Ђ�
�����̑��������헧���A���Ă��Ċy�����Ȃ�A����ȃ��[�N�V���b�v�B�C�n�b�u������M�I�������Ɏ��g�݁A�O
���ڂɂ́w�R in �P�x��S���ŕ������䎌�����u���Ĕ��\����i�܂����j�A�ƁB�ق�Ƃ��ɂ����Ȃ����Ⴄ�̂ł́A�Ǝv
�킹��M�̍����Ɛ����̂��郏�[�N�V���b�v�A�ƂȂ����B
���ۉ����𗬃Z�~�i�[�@�p���X�`�i���W
�p���X�`�i�̉�����̌����悤�I
���ҁF�щp��

�p���X�`�i�ʼn����ƒn��Љ�̔Z���ȊW�������H����C�G�X�V�A�^�[�̃C�n�b�u�E�U�n�_�@���𒆐S�ɔo�D
���g�̑̌��Ɋ�Â��đn�삳�ꂽ�Y�ȁw�Rin �P�x���L�����v�̎q�������Ƃ̋����n��Y�Ȃ�ǂ݁A���N��
�n���đ��������̒��A����ȏ��ɂ����ĉ������ǂ̂悤�Ȗ�����Ӗ������̂����l���A�����ɌX�̑�
���Ɋ�Â���i���̕��@��T���Ă݂����Ǝv���܂��B
�u�t�F�C�n�b�u�E�U�n�_�@�@ Ihab Zahdeh
in�@����
�����F2015�N8��2���i���j�`5���i���j
���F�|�\�ԓ`��
in �S�R
�����F2015�N8��6���i�j�`9���i���j
���F�S�R�s���y�E�����𗬊فi�~���[�J�������Ɗفj
�p���X�`�i�������{�����_���쐼�ݒn��w�u�����s�����_�Ƃ���C�G�X�V�A�^�[�́A���N�ɂ킽���đ����C�X��
�G���E�p���X�`�i�����̒��A�������u���a�̕���v�ƍl���A�����O�ł̐��͓I�Ȋ�����W�J���Ă���B�܂��A���
���ْ̋�����������q�������ւ̐S���I�J���̎�i�Ƃ��Ẳ����̊��p��n��S�̂̊w�Z�ƘA�g�����H�B
�q�������ɒ��ڐڂ��鋳�t�����ɉ����I�Ȏ�@�̎w�����s�����Ƃɂ���āA�n��̊w�Z�ƌ����L�@�I�ɂ�
���镶��������W�J���Ă���B����̓C�n�b�u�E�U�n�_�@�������S�ƂȂ�A�o�D���g�̑̌������Ƃɑn�삳�ꂽ
�w3 in �P�x��ǂށB����́u���̉����v���R���Z�v�g�Ƃ���e���T�E�|���h�[�����ۉ����R���y�e�B�V�����i�C�^���A�E�~
���m�j�ň�ʂ��l���A���ۓI�]���̍�����i�ł���B���{�ł�2013�N12���Ɂu�����n�悩�琶�܂ꂽ�����T�v
�i��ÁF������/���v�Вc�@�l���ۉ���������{�Z���^�[�A���ÁF�����|�p����j�Ń��[�f�B���O�㉉���ꂽ�B��
����L�����v�ɕ�炷�q�������ƈꏏ�Ƀ��[�N�V���b�v�����{���Ȃ���q�������̑̌�����ނ��č\�����ꂽ
�n���i�wPlaying in a Camp�x�A�wLittle Adults�x���ǂށB�����ɎQ���҂ƂƂ��ɑn��̎��݂����H���A��������
���ɒT���Ă݂����B
�ŏI���́w3 in 1�x���[�f�B���O�㉉�ƃV���|�W�E�������{�B
�y�u�t�Љ�z�C�n�b�u�E�U�n�_�@ Ihab Zahdeh
1977�N�p���X�`�i�A�w�u�����s���܂�B1997�N���Z�݊w�����o�D�E�X�^�b�t�Ƃ��Ċ����B2002�N�ɃG���T����
�ʐM����w�ɂăA���r�A��w�Ȃ𑲋ƌ�A2004�N�|�[�����h�A�O�_�j�X�N��w�ɂăh���}�E�C���E�G�f���P�[�V����
�R�[�X���C���B�C�G�X�V�A�^�[�n�������o�[�B2012�N�����{��NPO�@�l�s�[�X�r���_�[�Y�ƃC�G�X�V�A�^�[�ɂ�
��A�����E�\�[�V�������[�J�[��ΏۂƂ����g���[�j���O�v���O�����uYes 4 Future�v�ɂāA���[���v���C�E�C���v��
�o�C�[�[�V�����̃��[�N�V���b�v��S������B�����c�ւ̋q���������B2010�N�ɂ̓A���J�T�o�E�V�A�^�[�ɂ��
�w��̉��̕���x���{�����ɎQ���A2014�N�ɂ́u�����n�悩�琶�܂ꂽ����5�|Part2�v�ŗ����B
in ����
�����[�N�V���b�v�@�p���X�`�i�̋Y�Ȃ�ǂށ��n��̎���
�Y�ȁw3 in 1�x�A�wPlaying in a Camp�x�A�wLittle Adults�x
8��2���i���j14:00�`17:00�@
8��3���i���j18:30�`21:30�@
8��4���i�j18:30�`21:30
�����[�f�B���O�w�R in �P�x���V���|�W�E��
8��5���i���j19:00�`21:30�@
���[�f�B���O
���o�F�H�t��肦�iNPO�@�l�O���V�I�u���I�j
�o���F���J�쐪�i�A�͒ÍO���A�����B��
�V���|�W�E��
�p���X�`�i�̉��������`�Љ�Ƃ̊W����鉉��
�p�l���X�g�F�C�n�b�u�E�U�n�_�@�A�דc�a�]�i�C�X���G�����w�E�����A������w�j�A�H�t������@
�i��F�щp��
�������/�|�\�ԓ`��
�����s�V�h�搼�V�h6-12-30�@TEL:03�|5909�|3066
�������g���ۃm�����u���V�h�v�o��2���k��7��
in �S�R
���[�N�V���b�v�@�p���X�`�i�̋Y�Ȃ�ǂށ��n��̎���
�Y�ȁw3 in 1�x�A�wPlaying in a Camp�x�A�wLittle Adults�x
8��6���i�j19:00�`21:30
8��7���i���j19:00�`21:30
8��8���i�y�j14:00�`17:00�A18:00�`21:00�@
���[�f�B���O�w�R in �P�x�����N�`���[
8��9���i���j14:00�`17:00
���[�f�B���O
���o�F��c���i���c���j�b�g�E���r�b�c�j
�o���F����s�l�A���a��A��������
�C�n�b�u�E�U�n�_�@�ɂ�郌�N�`���[
�p���X�`�i�̉��������`���������̑̌������鉉��
�S�R���/�S�R�s���y�E�����𗬊فi�~���[�J�������Ɗفj
�������S�R�s�J���꒚��1��1�� TEL:024-924-3715
�S�R�w�O����[�R�o�R��s���܂��́A�x�s���u�O�����h����v���ԁB
�������́A������z�Պۉ��u�����̈�ّO�v���ԁB
�e�H���̏��v���Ԃ́A��10���B
�y���\���݊T�v�z
�ΏہF�����ƂƂ��ĉ����n��Ɍg�����i���o�ƁA�o�D�Ȃǁj
����F20��
�Q����F3,000�~�i�l���ԁj
������������A���[�N�V���b�v���w500�~�i��j
�ŏI���݂̂̏ꍇ�@500�~
����F20��
�������ϑ����Ɓu����27�N�x����̕�����n������V�i�|�p�ƈ琬���Ɓv
�y��Áz������/��ʎВc�@�l���{���o�ҋ���
�y���́z�����c�������@�l�s�[�X�r���_�[�Y/���v�Вc�@�l���ۉ���������{�Z���^�[/���c���j�b�g�E���r�b
�c
�y����z��ʎВc�@�l���{���o�ҋ���
�w3 in 1�x�@�|��F���J����݁A�wPlaying in a Camp�x,�wLittle Adults�x�@�|��F���R�L�q�@����F�n�Ӑ^��
��ʎВc�@�l���{���o�ҋ���@
��160-0023�@�����s�V�h�搼�V�h6�|12�|30�@�|�\�ԓ`��3F
TEL�F03�|5909�|3074�@FAX�F03�|5909�|3075�@HP��http://jda.jp/
�S���F�щp���A�����I�A���������A���Ƌ`���A��؋I�q�A���X�؉�F
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�w���x�`�[���̍��g���U�̈��݉��i�Q���҂͑S���ł͂Ȃ��j�B����Ȃɂ������g�͖ő��ɂȂ��B������e��
�[�����I�������̊F�̏Ί�ɂ悭����Ă���B�������̂��ƊO���̎d�����������Ɠ����Ă��邽�ߓ����A�z
�[���ł̌����͂��a���ƂȂ�B���A�����܂��B�B

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ���N�������B�܂�4����B�\�ɏo��A���\�A�������B�U�����邩�B���N�������͖̂��̓r���A�́A���̂���������
���o��B�ꏏ�ɕ�炵�Ă���悤�����A�ʂ̒j�����ĕ������o�Ă���ƌ�����i�j�C�Â��ƊR����Ԃɏ����
�܂ܗ����Ă��邪���̂��������D�u�Ƒޏꂷ��i�����A�쌀�j
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�w�� ���V�Q�x�y���A�e����������̓��u�̑�N�A�g�i����`���ɗ��Ă��ꂽ��B�Â�����̒��Ԃ����Ă���
��Ƃق��Ƃ����B

�ŁA�{�ԏI����āA�炵���I���đł��グ�ł��B�������\���������킩��Ȃ��p�^�[�������ǁA����͌l
�I�ɂ�����Ɵ��A���⊴�S�[�����̂�����A���H�������āH����̓q�E�~�E�c�E�E�B�܂��A�O�\�N�ڂɂ��Ă�
�u�ďo���v�݂����ȁA���낢��ƁE�E�E�B

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ���o�A�����A���s��O���̎�������B�n�܂�܂ł͍�邱�Ƃ���A���ꂵ�����ɖ������������낻�됧���
�C�i���s��j���ɂ̂��|����(��) �Ƃ�����A�A�����ȁA�����ɓ����ăm���}�������Ă������I�ɔ����Ă����o��
�҂����Ă��肪��������B������������{����������A���I����Ɋ��ӂ̈�O�B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
���悢����������B
�݂ȂŐ������Ă̕���L�O�B�e�ł����B

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�w�� ���V�Q�x�@�m�����
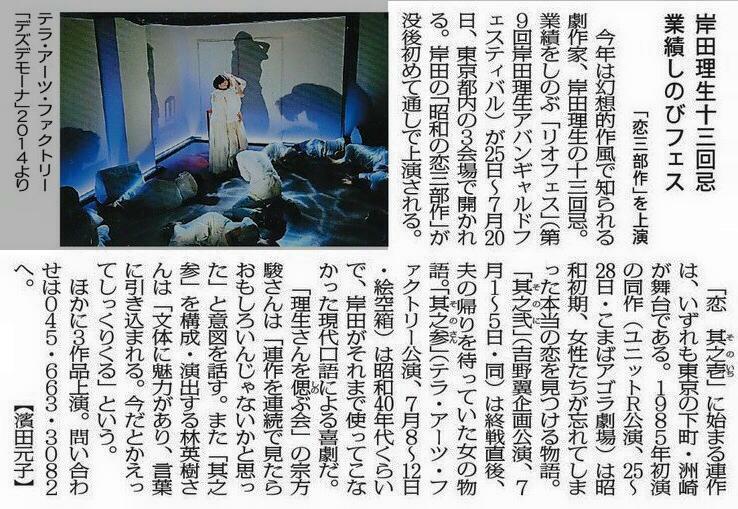
����A�ߑ�������2��ڂ̒ʂ��m�Î��{�B2�T�ԑO�ɒʂ����o����Ƃ��낢��Ǝ蓖�Ă��o����̂ł��肪��
���B�V���ɂ��Ɗݓc�����́u���z�I�ȍ앗�v�̍�Ƃ��������B�Ȃ�قǔޏ��̕���͂ǂ���u���z�I�v�������B
�����Ĕ��ɋ��łŁu��̐��v���������o�D�́����́��������ɂ͂������݂��Ă����B���X�����d�����C�z��
�Y�킹�鏗�D�w�A�����Ŗ쐫�I�Ȓj�D�w�B�B�B
�������A�ݓc��������̍�i�Ɉ������O���������B�����1991�N�Ƀ^�C�j�C�A���X�̃v���f���[�X�ŏ㉉��
�ꂽ�w�o���̖�x�ł���B�Ȏq�̂��邵���Ȃ��i�����̏オ��Ȃ��j���N�̃T�����[�}���ƉA�̂���Ⴂ������
�̕s�Ϙb�ŁA���Ƃ��ƃe���r�p�ɏ����ꂽ�V�i���I�i�e���r�ł͍Ⴆ�Ȃ����N�j��~��x�v���A�Ⴂ�����͓���
�����肪������j��p�ɏ������������̂��B�������́u�ݓc�������{�y�V�c�v�̔��d�~���������A�u������
�オ��Ȃ��T�����[�}���j�v�͉��̂����ɔ��H�̖�������B����܂Ŏ�������������i�����o���͂��Ȃ���
�����̂����A�[��Q���ɗ�������d�b���������Ă��ďo������悤���������Ƃ��ꂽ�B���I����̌��c�ɑf
���炵���j�D�w����������̂ɉ��́A�������H�Ǝv�����m���Ɂu�������オ��Ȃ��v�A�u�Ⴆ�Ȃ��v�A�u��
���Ȃ��v������͑������M�������āA�����߂�s�ނ��Ƃ̏o���錩���ȁ����́������L�����ݓc�������̋���
�Ȓj�D�w���A����Ȃ������̕������͂܂��Ă����̂�������Ȃ��B������Ƃ��������ł͂Ȃ����R�̂ł����ɗ�
�������~���������̂��Ǝv�����A�m���ɂ��̂܂ܖ��Əd�Ȃ銴���͂������i�j�@���т��オ��Ȃ��̂ɓ��䂩
��������ł����Ă��܂��̂�����A�{���ɂЂǂ��z���i���j���A�~��x���v�̘b�ł��B
�܁A�]�v�Șb�͕ʂɂ��āw�� ���V�Q�x�̒ʂ��m�Â����Ȃ���A���̃e���r�p�ɏ�����A�������𒆐S�ɂ���
�w�o���̖�x�̎��́A�����Ƃ��̐̂ɖY�ꂩ���Ă������G���������̂��S���Ă��闈��̂������o���Ă���B
�Ȃ��T�����[�}���Ȃ̂��낤�H���́A�����̏オ��Ȃ��A�Ȃ̂��낤�H���́A�c�n�̎�w�i�u�c�n�ȁv�̕�����
���̃C���[�W�������Ƃ��j�Ȃ̂��낤�H���́A�������ŏ������̂��낤�H�Ȃ��A�u���v�Ƃ����^�C�g���̂Ȃ̂���
���H�l����l����قNJݓc�����̏p���ɂ͂܂��Ă���B������ɂ��Ă��ݓc�����ł���B�o�D�w�͔ޏ��̂�
�Ƃ̗́A��b�̗́A��{�̗͂ɏ悹���ǂ�ǂ�ϖe������B�o���邾�����o�͗]�v�Ȃ��Ƃ������A�V��
�v���ɔo�D�w�A���肪���̂���D�G�ȃX�^�b�t�w�i���ꂾ���͕�A�f���炵���l�ނ��W�����Ă���j�A�����Ĉ�
���A�u�쌀�v���ɏ����ꂩ���h���I�ȍ앗�A�������悭�`���Ƃ����Ԃs���̂��閣�f�I�ȑ�{�ɐg����
���A���ɐg��C����̂݁B�u����Ȃ������ȁv���o�Ƃ͎���Ɏx�����āu���o�v�����Ă�����Ă���̂ł���i�j
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
������̃h���}���`���Ƒ̂���̉�����u���v�̋G�߁`
�w�� ���V�Q�x�@�ݓc������A�щp�����F
����̌m�ÂŁA�͂��߂́u�R���f�B�v�Ǝv�����₢�̊Ԃɂ����������G�ɒj���̌��э������������ݏo������
��̃h���}���֔��W���A���ꂪ��������R��ƂȂ�6��i�S�V��̂����j�̋l�߂��s�����B������̃h���}���́�
�g�̂̃h���}���ƈ�̂ł���B�u���v�Ƃ͐��Ƒ̂���̉�����v�t���ɋN����ʉߋV��ł�����B��l�i�Љ�j
�ɂȂ邱�ƂŐl�͂����r������B�������ݓc�����͍�i�����������邱�ƂŁu�v�t���v��ێ����������l�B�B�B
�m�ÏI����č���e�����Q���j���w�ɗU��ꋏ�����֓��s�A�ݓc�����ɂ��Č�荇���B�^���ʈȏ�Ɍ���
���G�l���M�[�i�W���́j���g���e���̕���B���ꂽ�����o�[�ł�������̌����͂��Ȃ�n�[�h�A���炾�Ɋ���
��B���̕���Ȃ疈��m�Ì�A�{�Ԍ���݂ɍs����]�T�A�̗͂��c���Ă��Ă��e������͂Ȃ��Ȃ������͍s��
�Ȃ��B���ꂩ��{�ԂɌ����đ̒��Ǘ����X�g�C�b�N�ɂ��肢���܂��Ƌ������œ`����B
���߂ė�������A�����Ȃ��Ǝv�����B
�����������Ďg��Ȃ������������𑽗p��������́w�� ���V�Q�x�B�������A�\�w�I�ɏ����Ă�悤�Ɏv��
�镔�������Ԃ����̐����[�݂����B���ƂƂ��ĕ\�ʂɕ\��Ȃ������A�[�w�ӎ��̕�����O�����ԓI��
�~�����ĂĂ���B���́u���Ԃ��̂��Ƃv�̐��݂�����͔���������܂Œm���Ă�������ł����ݓc�����́u��
�̊�v�Ƃ����������Ƃ����Ƃ������ݓc�������Ĕ��������v���ł���B�ʁi�����āj�ɕ����Ă������ƂɎ���ꂿ
�Ⴀ�[�w�ɉQ����������̃h���}���͌����Ă��Ȃ��B������g�̂ş��ݏo���A�~���o���Ă��銴���̍�Ƃ������
���Č����ė������̂��B���Ԃ�u��b���v��S�������Z�̃A�v���[�`�ł͌����Ă��Ȃ��A�����͕����オ���Ă���
���B���Ƒ̈�v�́u���v�����S�e�[�}�Ȃ̂�����A�����Ɛ[���Ƃ���ɂ���i��/���j���̂����݉������Ȃ��ƂȂ��
���B
�t�c�\�̐l�̃t�c�\�łȂ����́`
�N�����������Ă��āu�댯�v�����畁�i�͌����Ȃ��Ƃ���ɉ������߂Ă���u�����́v�ɘM��n�߂�t�c�[��
�l�i�t�c�[�Ȃ�ĂȂ��A�����玩���𗠐�t�c�[�����ƂŐ��Ԃ��猩���Ȃ��悤�ɂ���j�A������Ɓu�����߁v
�ɍ����B�Ղ߂鑤�͂��ł������߂��鑤�ɂȂ肤��̂�����B�u�t�c�[�v�̎�w���������菗�D�w�̃t�c�[
�̕\��̉��ɐ��荞��ł���u�t�c�[�v�łȂ����̂����ɓ��ɂ������Ȃ��Ă��Ėʔ����Ă��܂�Ȃ��B�����l��l�E
���Ă��܂�����B�����Ă����Ɛ����͕̂v�����B���}�ȃT�����[�}���̊�i���ʁj���Ă邯�ǁA���̒��ɔƐl
������i��������Ȃ��Ɨ\�z������A���̂��ƂōȂ����̕s���̓p�j�b�N�ɋ߂���Ԃɔ��W����j�B�Ɛl�͈��
�N���H���߂́u�����R���f�B�v�Ƃ��v���Ă������A���������Ă���~�X�e���[�H���Ƃ����v���Ă���A�����������͑�
���Ă��͂�Ă��ݓc�����B�e���r�h���}�̔@���A�ʑ������̔@���ȃ~�X�e���[�ł͂Ȃ��B�w�� ���V�Q�x�A�m��
�����قǖ��m�̗̈�ɓ����Ă���B���Жڌ����ė~�����B18�N�Ԃ�̏㉉�ł���B�e���Ƃ��Ă����܂�
��肽�����ڂ̈�ɓ������i���p�[�g���[�A����D.���[�A�[�́w�Ō�̉��x�A�ݓc�����́w���n���x�A���R�C�i
�́w���͗������܂ܖ����Ă���x�A�\�t�H�N���X�́w�A���`�S�l�[�x�B��肽����i�͂���������������̂ł͂�
���j�B
�����ڍׁ�http://www.geocities.jp/terra2001jp/
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�����ق̌��ꁄ�Ɛe�a����ꏊ�ɂ��邱�Ƃi������j
��9��ݓc�����A�o���M�����h�t�F�X�e�B�o���t�F�X�e�B�o���i���I�t�F�X2015�j�Q�� �i2015�N7��8���`12���j
�w�� ���V�Q�x��F�ݓc�����@���F�E���o�F�щp��
�ڍׁF�e���E�A�[�c�E�t�@�N�g���[HP��
http://www.geocities.jp/terra2001jp/page121.html
�w�� ���V�Q�x
���̍�i�̏������i1987�N�j�͌��c�̐��������Ԏ�������Ƃ̓Ǝ��̕��̂⌀����ɂ���Ė��ҊԂ̐g��
�����L����O����I�ȗ����A���L�̗̈悪�傫���`������Ă������̂Ǝv���B
�O�X��ɎQ���������I�t�F�X�̃e���Łw���n���i�}�e���A���^���n���j�x�́A�u�ݓc�����������{�y�V�c�v���W�c
���̒����ɗ��������ɍ��ꂽ��i�ŁA��͂�W�c����Z���Ɋl�����n�߂��e��2009�̎��قȂ��ނ̏W
�c���ɒ��悫�����ŗn�������݁A��������V���ȕ���Ƃ��čč\�����\�ۂ��邱�Ƃ��o�����B�������A����͂�
�̎��Ƃ͑S����Ԃ��قȂ�B
��Ԃ��قȂ�̂�����A�����ł��n���I�ł��邩�����`�ŒT��E�T���K�v������B�ŁA��T���̑e�����m��
�ł��Ȃ茩���Ă������̂��������B
��������`��������˂����������E�ց�
�ܑg�̎Ⴂ�c�n�̎�w�����̌������ތ��t�i�������̐��E�A���邢�́u���ԁv�j�ɓ���Ȃ������c�n�̎�w
�u���v�B��w�����ɑΗ����鑶�݂Ƃ��ēo�ꂷ��u�������ꂽ���v�́u���v�B�ޏ���͊ݓc�����̈���Ƃ��������
�����\����L���Ă���B��w�����̓���ɓ����o���Ȃ������u���v�͎������邵���Ȃ��u���v�͐��_�a�@�Ɋu����
���^���ɂ���B
�u���v�̎�����i�h��I���b�j�́����ق̌��ꁄ�ɒʂ�����̂Ŏ�w�����̈ˋ�����u�\�w�̌���v�i���Ƃ�
�Ă̌���E�L���`�R�~���j�P�[�V�����̃c�[���j�Ƃ͑��e��Ȃ��B�e���łł́u���v�̎������ق̌��ꁄ�Ƌ��U
���鑶�݂Ƃ��āu�F��ɂ��Đ����������t���c������C�ɐg�߂Ă������ł��낤�����v���ے��I�ɁA����
���͋L���̌��e�Ƃ��ēo�ꂳ����\��ł���i�����̑��ǂ̓o��A�u���v�̎�������ʁj
����͐��E������Ă���B�������͂��̌��ꂪ�`�����鐢�E�ɕ����߂��Ă���B�������甲���o�����߂�
�͐V���Ȍ���̊l�����K�v�ł���A�ݓc�����͂������낤�Ƃ��A�܂��u���ق̌���v�����l�̈Ӗ���L����B
�����炭����͌�������˂��������Ƃ���ɂ���A�����ق̌��ꁄ�Ɛe�a����ꏊ�ɂ��邱�Ƃi������j�A��
�̂ł͂Ȃ����B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�����Ή��̉��Z��Ԃ̍\���A���Ƃ������Ă����Ƃ���B����̂����Ƃ��傫�ȕǁA����ȕ����������B�哹���
�������ނȂ�i�����Ƃ��e�[�u�����x�����j�A�����p�ӂ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂Ő^����ɔ��f����K�v
������B��r�I�A�傫�ȕ����z�肵�č��ꂽ��{�B����������ȃX�y�[�X�Ɏ����Ă������������܂Ő���
�ɎU��߂���{������قǂȂ���������Ȃ��B�����͂��������G�ɏo���Ă���B
���āA����́u�� ���V�Q�v���B
���̒m���Ă���ݓc�����͂܂�ŕ�e�̂悤�Ɍ��c�����l���A��/�ޏ���̐����ɍ��킹�Č��t��a���o����
�i������Ƃ������i�O�����`���c�������j�B���̈Ӗ��ŋ��ɂ̖��Ҏv���A�D�����͗ނ��݂Ȃ��l�������B
����̑�{�͂��̌��c�̍Ő����A�����E�ł����ڂ̉Q���ł̍�i�B���c�͏����A��������������͋t�Ɋ�
�@���������Ă����B�u�����߁v�ɂ������芵��A�S�n�悳�������A����ɓ��������҂ɁA�����Ŏ~�܂��Ă̓_�����A
�������������������ŏ�������i�Ȃ̂��B��������C�ɂ������A���S���Ԃ��A�����čX�Ȃ鍂�݂Ɍ���
���ė~�����A�������������c���̐����ߒ��ƍ��킹����i�B�����i80�N��j�����Ƃ��[�������W�c����ێ�������
�c�B���̔Ր̑̐��̒��ō��t��Ƃ������Ă��̌��t�ɐg���S�����܂�������҂Ɉ�x������̂Ă�Ə�
������{�B�i�㉉�����̕���́j�o���̗ǂ������͂킩��Ȃ��B�������A�����ɔޏ��̖��҂ւ̈���̐[�����m
���ɂ��邱�Ƃ́A�킩��B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6���ڂ̌m�Â����B��T��7��̂����A4��܂ő�G�c�ɗ�������߁A�����͊�����l���ł̓�����v����
��ʂ������ׂ������߂�B�c�n�̕v�w�T�g10�l�������ȕ���ɓ����ɕʁX�̉ƒ���ɂ���ŏ��̃V�[���Q���
�`�ʂƂ�������ԍ\�z�A�~�U���Z�[�k�ɁA�Ȃ��m�b�i���čl���ɍl���������Ƃ����̉��A���ꑽ��Ԃ̍��A�s
���R�����Ǖs���R�Ɋ��������Ȃ��H�v�A�������������B���̒��Œc�n�ւ̐N���҂����đ呛���V�[���B��
����25�b�̏�ʁA������13�l�������ȋ�Ԃ��ɓ������J���_���g���B���x����蒼���őS�̂��ł܂�܂�
�ɂ͖��Ґw���������B�����l�ł����I�ʂ̈ړ���ʂ��O���������ғ��m���Ԃ���Ȃ��悤�����ڂɔ���
���Ȃ�悤�����̐����B�܂�Ńp�Y�������Ă��銴���B
�u�ݓc�����������Ďg��Ȃ������������i��������ꂽ���{��j�ɂ��쌀�v�Ƃ����ِF��B�R���f�B�ŋ���n
�ɃV���[���ȏ�ʂ������A���I�W�J�B���Ԑ��n�т̋L�������҂�����ʂِ͈l�̓����ŁB�������삵��
���������i1980�N��j�̍앗�Ƃ҂�����d�Ȃ鐢�E�ςƍ앗�B�Ƃ������A�������Ɏ����Ă��Ă��܂����H
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�u�� ���V�Q�v�m�Îl���ڏI���B
�ŋ��̎n�܂�ł���1�ꏗ���V�[���A�������Ɩʔ����𑝂��B�P�ꂩ��3��܂ł�40���͑e����̒i�K�����[
���ϋq���䂫�t������育��������B���Ƃ͌㔼���ǂ������グ�Ă������B����͖��҂������́A���o�͂�
�̂��߂̓y�U��[�������A�����Ĉꏏ�ɕ���n������Ƃ����e�����W�c�n��̕��@���Y�ȏ㉉�ɂ�
�����Ă��������B���҂��������������������Ƃ��Ă���B����͏o����16���̑��������߂ăe���̕�����ꏏ��
�邪�A�����������y�U�ňꏏ�ɕ����������ǂ����u�ɂȂ����B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
���u��ҁv�����e����鐢�E��
DCS�i�h�����S�E�N���G�C�e�B�u�E�X�N�[���j�̎��ƁA�I����Ă��̂܂܉H�c��`�֒��s�B�����̎��Ƃ͑����E�G�`
���[�h�B�傢�ɏ����e�A���k�������������Ă����B
�|�p�Ƃ͓��ʂȑ��݂ł���B�����A�S�b�z�Ɠ����̎��Y�Ƃ⒬�̗L�͎҂��l�������ƂȂ������A�����̐l�X��
�Ƃ��ĉ��̉v���Ȃ��S�b�z�����̂Ă��邾�낤�B�������A���̉�X�ɂ͓����̂��̕��͉��̈Ӗ����Ȃ����S�b
�z�͏d�v�Ȃ̂ł���B�l�̖��͓������l�A�Ƃ͋ߑ�q���[�}�j�Y���̌��O�ł���A����͂���ő厖�Ȃ��Ƃ�
���A����Ől�̉��l�͂��̐l�̐�������\�͂Ɛ藣�����Ƃ͏o���Ȃ����Ƃ��m�����B�Љ�͌��݂����ő���
������̂ł͂Ȃ��A�����ɑ��Ă̐ӔC������B���̂��߂Ɍ|�p�Ƃ͂ƂĂ��M�d�ȑ��݂Ȃ̂��B
�S�����ւŕ����ցB19���̕ցA�r�W�l�X�}���������B��l�ɓ�����������Ă���j���炯�A�r�W�l�X�}����
�炯�B2�����x�A�����B�t�x�A�Ȃ̊w�����BTTC�Ŗ��É��ɒʂ������̕����̐V�����̎ԓ����v���o���B�r
�W�l�X�}���̌쑗��ԏ�Ԃ������B
�K�ٗp���������Ƃ͌����Ă��A���ău���[�J���[�Ő��K�������҂����͐����Ƃ��O���[�o�����̔g�Ő�
�ނ��K�ցA�������u�z���C�g�J���[�v�͕ς�炸���̑w������A�Ƃ������Ƃ��B�K���������Ƃ����͔̂_
�Ə]���҂̌����A�����Ə]���҂̌����ƃT�[�r�X�Y�Ƃ̑����ƕs���̊W���낤�B
��s�@�̒��Ŋݓc�����́w���`���̎Q�`�x�ǂށB�c�n�̎�w�ƒ����T�����[�}�����E���`����Ă���B���̔�
���Ȑ��E�����m�ɁA�����ɂ��̔���ꖇ�߂���ƉB�����ꂽ�ł��I�o����B�瑊�Ȑ��E�A���Ԃɗ����͓��肽
���Ȃ��A�������肽���Ȃ��B������A�����̓���I�B�T�����[�}���i��ЗD�恁�o�ϗD�承�l�ς̐��E�j����
�����I����I�ɊO�ꂽ�B���������������ƕʂ̓���I�B�����ăr�W�l�X�Ƃ��Ẳ����ł͂Ȃ��A�u�|�p������
���Ẳ����v�i�ׂ���Ȃ����ǂ��K�v�����鉉���j�ɎQ�������̂��B
�����h�̗ǎ��A�U�P�I�ȁu�q���[�}�j�Y���v����̓��S�`���ꂪ�w���x�̐��E�ς��`�����Ă���B�]�v�ҁA����
�́i��ҁj�����Ă��������E�A��҂�������鐢�E�B�N�ł�����҂ɂȂ链�錻�݂��炱�̍�i������Ƌɂ߂�
�����I�i�|�X�g�k�ЎЉ�j�Ȏ��������Ă���B�َ��ȑ��݂�r�����铯��������������Љ�ւ̍����A�Ɠ���
�ɂ����́u�����ʂ��ҁv�ւ̗D�����ɗ��ł����ꂽ���E�B
�܂��͏o���҂�������A���R���̃e�[�}���B���̐��E�ς����L�ł���҂�����������̂��ۑ�B
���ĎЉ�ł͎Љ�ɋ��ꏊ�̂Ȃ���҂��ߌ����A�C�X�������ɎQ������ƌ�����B�����������ۂ̍���ɂ�
����Ƃ��̍�i�͐[���֘A���Ă���A�Ǝv�����B���{�������Ԃ�A�������炭�Ȃ��Ă����B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�قȂ���̂Ƃ̌𗬂͎��E���
�`�����̕s�\���Ƃ̑Λ��A���ق��邽�߂Ɂ`
��N�P�Q���̂h�s�h�i���ۉ�������j���{�Z���^�[��搧��u�����n�悩�琶�܂ꂽ�����U�v�Ɋւ��ď����l��������
��Y��ʂ��������i�m�[�g�j���Ă����B
�w�R����X�^�A�̃o���b�h�x�i�j���E�p���f�B��A�t�j/�C�X���G���j�͏W�c�n��ł����A������l�Ԃ������\����
��A��i���邱�Ƃ�O��Ƃ����t�B�W�J���ȕ���ł���B���̌��t�i�e�N�X�g�j�������g���A���{��œ��{�l��
�o�Ƃ����{�l�o�D�ɂ���ă��[�f�B���O����Ƃ������Ƃ̓e�N�X�g�̈Ӗ������ɕs���ȃR���e�N�X�g�i�����j��
���Ⴞ���łȂ��A���̕\�����@�ɉ����Ă��傫�Ș�����������B�����O��ɂ��܂��O���ɒu���ĉ��o���l����
�K�v������A�Ƃ������Ƃ����������{�l�ɗv������B�X�Ɂu���[�f�B���O�v�Ƃ����\�����@�̕s�\������E����
���݉�����B�����́u�ǁv��\�ߒm������ł���ł���邩���Ȃ����̔��f�́A����́u���������v�̍�i
�I����V���|�W�E�����܂߂��e�[�}�̌��āA�O���E���h�f�U�C�������鑤�ɂ��Ȃ�̏n�l�̎��ԂƎv�l��Ƃ�
���߂邱�ƂɂȂ����B���ۂɃe�N�X�g�i�p����{�j����肵�Ă��炱����u�����n�悩�琶�܂ꂽ�����U�v�ł�낤
�ƌ��肷��܂łɂ͌���ł̓ǂݍ��݂ɂ��Ȃ�̎��Ԃ�v���邱�ƂɂȂ����B���G�ȍ\������������i�ł����
�����ɕ��G�Ȗ��A�܂���Q�҂Ɣ�Q�҂̂˂���̍\�������������̂�����ł���A���ꂪ��������ɂ͔�
�ꂾ���łȂ����قƂ̑Λ���҂ɗv�����邩��ł���B�����猾�t�����ł̓ǂݍ��݂ɗ��܂炸���t�ɕ�
���オ���Ă��Ȃ������ɑz�����@�艺���Ă̍�Ƃ��K�v�ƂȂ����̂ł���B
�h���b�O�N�C�[���Ƃ������ʂ���鑤�̗���̐ݒ肪����ɗv������A����͒P�Ɂu���v�Ƃ����ʒu�Â��Ɍ���
���ꂸ�A�N���b�҂ɂȂ邩�Ƃ������Ɛ[���ւ��B�킩�肸�炯��ΐ푈�Ɋւ�����{�l�̗���ɒu������
��悢�B�푈�̉��Q�҂Ƃ��Ă����ɗ����A�����ɂ͔�Q�҂̉Ƒ��A���Ƃ��Β�����t�B���s���œ��{�R�̎c�s
�s�ׂ��Ƒ����l�X�������Ƃ�����ǂ��ł��낤�B��Q�҂̗���Ŕ��ꂷ��ꍇ�Ƃ͗l�����قɂ���B��蕡
�G�ȍ\���A����͔���҂̃A�C�f���e�B�e�B���̂�[���������邱�Ƃ�v���A���̔w�i�̗������v������Ă����
�̂ł���B
����Łu����͋ɂ߂ăp�[�\�i���ȍ�i�v�ƌJ��Ԃ��������Ă�����҂̃j���E�p���f�B�����g�����{�l���o��
�ɂ����{��ł̏㉉�ɓ��������a����������悤�ŁA�m�Éߒ��ɗ�������Ƃ�������]���Ă����B���{�l
���ǂ��܂Ŕނ́u�p�[�\�i���v�ȕ����𗝉��ł���̂��H�����͉��^�I�ł������Ǝv����B���̉��^�����z
����̂Ɍ��ǁA���ĊςĂ�����Ď��������Ƃ͑S���Ⴄ���̂Ǝ���������A���������X�ɈႢ�̏�ɂ�����͂���
�ňӋ`������Ɣ[������܂ŏt����ڐG���n�܂�P�Q���܂Ŋ|�������ƌ�����B�P�ꖯ���Ƃ����v�����݂��x�z
�I�ȓ��{�l�ɂ���ď㉉����邱�Ƃ͂��Ƃ��Ƒ����Ѓ����o�[�ɂ���č��ꂽ���̂Ƃ̓A�v���[�`�������ƈ�
�Ȃ�ł��낤�B
�p���X�`�i��̂̓����Ґ��������֗^���Ă����i�A������u���l���v�ł����Ȃ����{�l����邱�Ƃɂ��A��
���i���Ɋ���ړ����A������������Ή��̖��ł�����A�ŋ�����������Ƃ������z�j�̕s�\����˂�����
���̂Ƃ��ĈӖ�������B�������A�s�\��������Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�s�\����O��ɂ��ẴA�v���[�`����
��͂��B��������{�l�ɓ˂�������i�������Ǝv���B
���Q�҂̑��ɗ������A����̒��ŃA���u�̏��N����˂��������Ɂu�C�ɂ���ȁA�����̏��N���v�Ɠ�������
�琺���|����ꂽ�u�ԁA�ނ͉��Z���~���A���������ĉ��Z�ȑO�̎����ɖ߂蕨�ꁁ���\�Ƃ��Ẳ�����
������o�Č��̒��f��������B�����āu���݂�v�ł͂Ȃ��B ��邱�Ƃ̕s�\���A�������t�B�N�V�����Ƃ����\��
�`���̕s�\���ɓ˂�������B����A�ނ�̉���������ɂ���č��ꕨ����鉉���̋��\���Ƃ����g�g��
�͕ʂ̏ꏊ�ɗ����Ƃ������A����̉��Q�����p���𔘂��A�ϋq�̔��f��v�l�𑣂��̂ł���B�܂茀����
�������Ȃ������A�Ȃ̂��B
�u�ٕ����𗬁v�͗e�Ղł͂Ȃ��B���{���x�̗����͓��{�l�ł��e�Ղł͂Ȃ��B�������A�e�Ղł͂Ȃ�����n�߂�
�̂��B�܂��͐ڐG����A���Ƃ��\�ʂ���ł��B���̈Ӗ��Ō��t�������͕̂\�ʂ�����������Ƃ�������B��
�t�̉��ɂ͌��t�ɂ͏o���Ȃ����ق�����A���̒��ق͍��ʂ��鑤�A�ア����ɂ���҂ɂ͏�ɋ������
�钾�ق̏d�������B���̒��ق܂Ő[�߂Ă̋��L�̈ӎu�Ǝp���̒��ŏ��߂ča�͐Ȃ�A�����̕��͏k�܂�
�Ă���B�n����̂̓����Ґ��Ɋ��Y���ԓx�������ƂŁu�𗬁v�́A���邢�͋����A�ĉ��W�̔��͊J�����
����ƌ�����B�����ɂ�����𗬂Ƃ͂��������v���Z�X�܂��钆�ŗe�Ղł͂Ȃ��������ł͂Ȃ��A�Ƃ�������
�������ݏo���ׂ��ł���B
�����n�悩�琶�܂ꂽ���� �V���[�Y6
�����ԁ@2014�N12��19��(��)�`23��(�E�j)
�����@�����|�p����A�g���G�E�G�X�g
�y��i����z
�w�R����X�^�A�̃o���b�h�iBallad of the Burning Star�j�x�iUK/�C�X���G���j
�����h�������_�Ƃ��鑽���Ќ��c�@Theatre Ad Infinitum�@�ɂ���Đ��삳��A��N�̃G�f�B���o���E�t�����W�t�F�X
�e�B�o���ő��܁A���݁A�p���c�A�[���̍�i�B���c�̓p���̃W���b�N�E���R�b�N���ۉ����w�Z�̑��Ɛ�����
�ɂ���Č������ꂽ�t�B�W�J���V�A�^�[����{�Ƃ���c�̂ł���B���̍�i�̍�E���o�E�剉��Nir Paldi�̓C�X��
�G���o�g�A�p���X�`�i�����Ɂu�C�X���G�����v�Ƃ��ĂƂ炦�A�����Ɛ�̂��C�X���G���l�̐S���ɂǂ̂�
���ȉe���ƕ���������N�����Ă��邩���u�L���o���[�X�^�C���v���g���ĕ`���o���Ă���B
|
|
|
|

